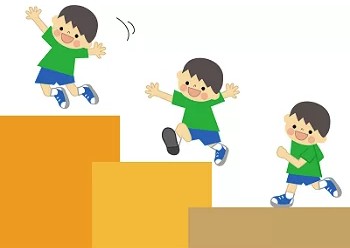J-rock (skrócona wersja nazwy japanese rock) to jeden z najpopularniejszych nurtów japońskiej muzyki rozrywkowej. Za nazwą J-rock kryje się muzyka pełna życia, która w mgnieniu oka potrafi porwać słuchacza. W latach 60. japońskie zespoły zaczęły czerpać z psychodelicznego rocka, który był w tamtym czasie bardzo popularny głównie w Stanach, ale nie tylko. W tamtym czasie Japończycy zaczęli eksperymentować również ze Space rockiem i innymi gatunkami. W latach 70. j-rock zaczął się zmieniać. Styl stał się bardziej folkowy, a wokaliści i autorzy tekstów zaczęli rozwijać własny warsztat pisarski. Jednym z nich był Kazuki Tomokawa. Ponadto zespoły takie jak Cosmos Factory i Kenso również znajdowały własne dźwięki, które były jednak bardziej progresywne […]